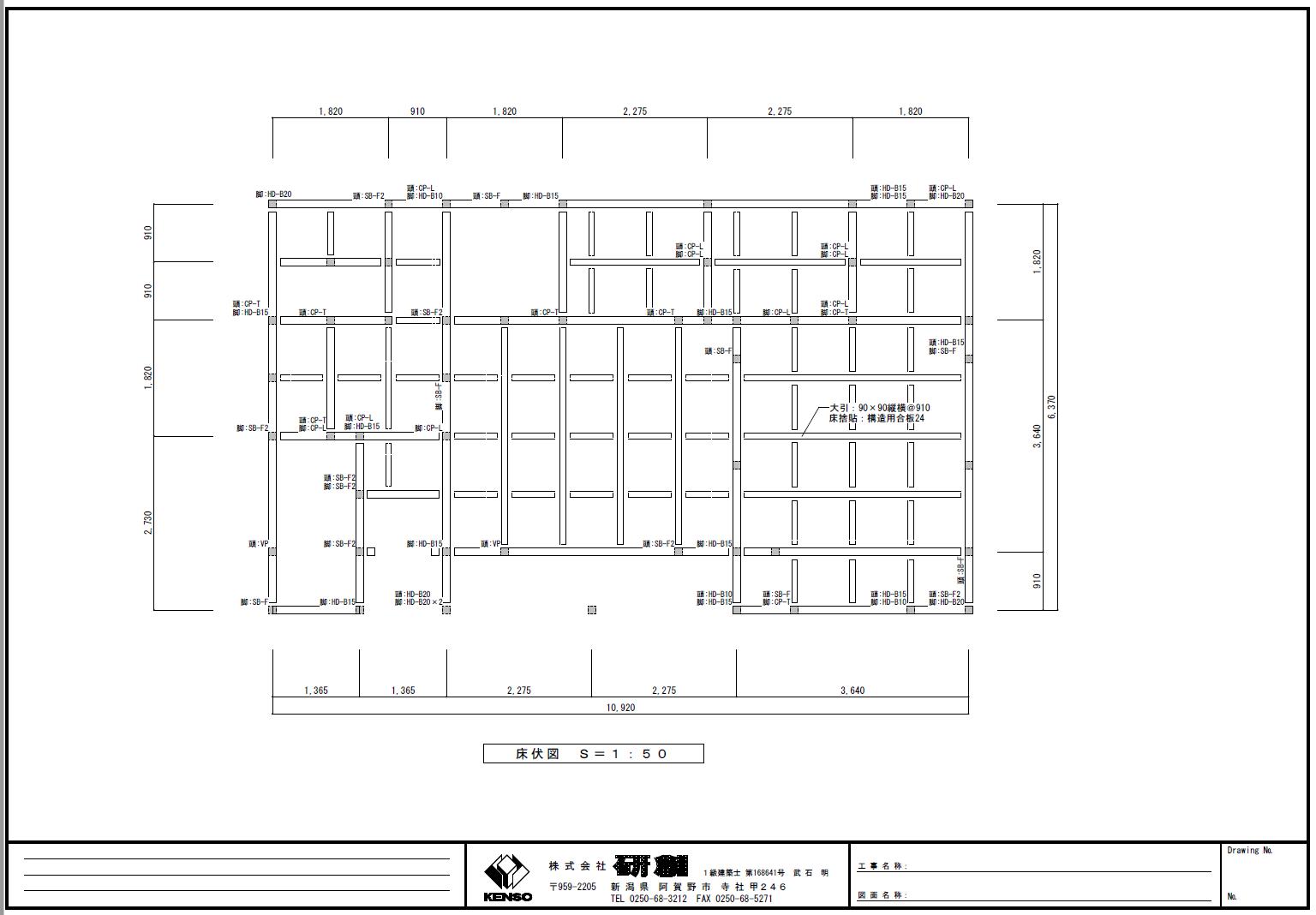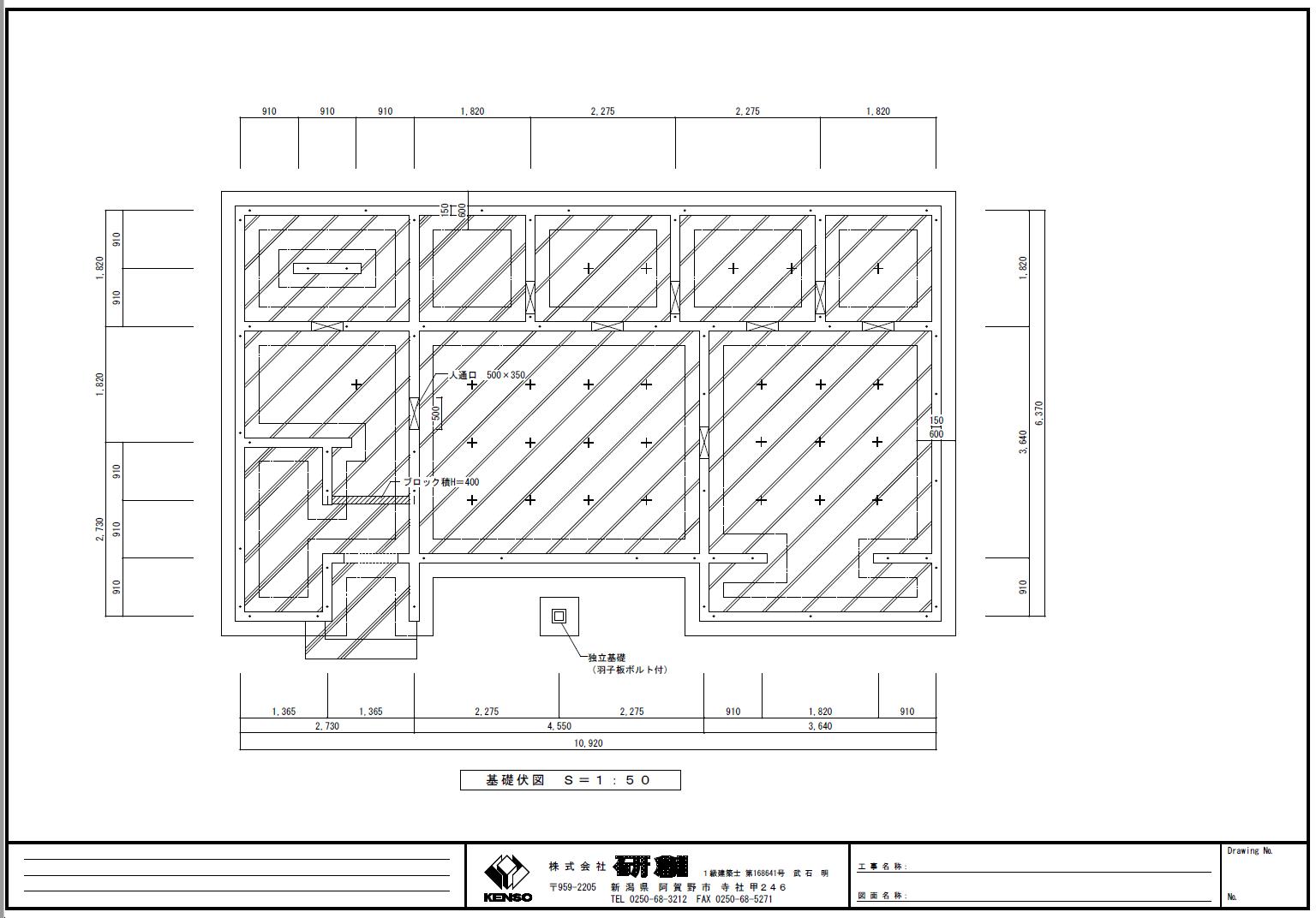風通しや日当たりを確保するため、南側に大きな開口部を取り、寒い北側は開口を最小限にして壁を多く配置する平面計画は、日本各地で多く見られます。
しかしこのようなプランは、全体では壁量を満足するが、耐力壁が偏在しているため、地震時には南側が大きく傾き、倒壊する恐れがあります。これは、阪神・淡路大震災の時多く見られた被害です。
建物の重さの中心を重心、堅さの中心を剛心といいます。重心はほぼ平面形の図心となります。
建物の堅さとは、耐力壁の強さ(壁倍率×長さ)です。例えば、南側も北側も同じ壁量であれば剛心は建物の中心となるが、壁量が北側に偏っていれば剛心も北側寄りになります。
また、重心と剛心にずれが生じている事を偏心といいます。ずれの長さ(偏心距離)は、大きければ大きいほど、水平力が作用した時の建物はねじれが大きくなり、倒壊する危険性が高まる。
たとえ偏心が小さくとも、外周部に壁が少なく中心部に偏在しているプランは、外周部が大きく振られやすい。